最新記事一覧
-
令和6年10月
-
十日十夜の善行を修める お十夜
10月から11月にかけ、各地の浄土宗寺院では「十夜法要」が営まれます。「お十夜」とも呼ばれますが、正式には「十日十夜法要」と言い、文字通り、十日間、昼夜にわたってお念仏をとなえ続けるもの。現在では、多くのお寺で日数を短縮して勤められており、特に浄土宗における十夜発祥の地である大本山光明寺(神奈川県鎌倉市)の十夜法要は、関東三大十夜の一つに数えられ、期間中には
-
心ゆくまで味わう 法然さまの『選択集』 第23回
浄土宗で〝第一の聖典〟と位置づけられる書物『選択本願念仏集』(『選択集』)。「極楽往生を遂げるためには、何より〝南無阿弥陀仏〟とお念仏をとなえること」とする浄土宗の教えを、宗祖法然上人(1133ー1212)が微に入り細に入り説き示された「念仏指南の書」ともいえるものです。大正大学教授・林田康順先生に解説していただきます。 第3章弥陀如来余行を以て往生の本願と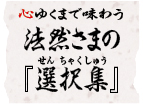
-
和装のおしゃれはまた別格!伝統守る名古屋のきもの店 優雅なきもの 杉本屋
愛知県名古屋市・高岳院檀信徒 名古屋市最大の繁華街・栄。その中心地から地下鉄で10分ほどの場所に、高岳というエリアがある。大手企業のビルが立ち並ぶオフィス街だが、裏通りは意外にも静かだ。その一角に見えてきたのは、大正14年(1925) から続く、きもの店「杉本屋」。 店の表にはいくつか反物がディスプレイされており、その美しさに魅了されてしまった。 「名古屋は
-
令和6年9月
-
十夜法要発祥の大本山光明寺 浄土宗開宗850年慶讃法要・十夜法要 10月12日~15日
10月12日から15日にかけて、大本山光明寺(=神奈川県鎌倉市・柴田哲彦台下) が浄土宗開宗850年慶讃法要と十夜法要を勤める。浄土宗開宗850年の正当となる本年、浄土宗の総本山や大本山では、開宗850年を迎えたことを喜びお念仏をとなえ、法然上人に報恩謝徳の想いを捧げることを目的に慶讃法要を勤めており、十夜法要発祥の寺である光明寺では、恒例の十夜法要に合わせ